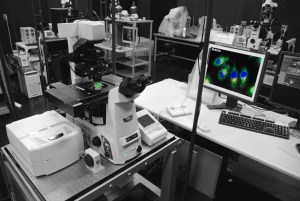利用の前に – 主な問い合わせと回答
当センターの利用について、よく寄せられる質問とその回答は、こちらをクリックしてご覧ください。
観察の前に – 打ち合わせや、機器の見学
センターの利用を希望する場合は、まず[お問合わせ]から、目的としている観察の概要をお伝えください。こちらで内容を確認した後、メールで連絡いたします。
時間がありますなら、まずは当センターで打ち合わせを行うとともに、当センターの各設備を直接ご覧になってもらうのが理想的です。私たちスタッフは、詳細な観察内容を直接うかがうことで、目的に応じた最適な観察方法を提案します。
このときに“観察が可能かどうかの確認”(この段階では、原則として直ちに使用可能な形式でのデータの持ち帰りは不可)として、サンプルの一つを持参してもらい、私たちがトライアル観察を行うことも可能です。
各顕微鏡の利用料金に関して
各顕微鏡の利用料金一覧
当センターの各顕微鏡は、大学のオープンファシリティ(北大の研究機器や設備の共同利用システム)に登録されており、消耗品の補充や機器利用の電気代等として、以下となる課金の徴収を、またオープンファシリティの規則により初回利用講習料(学内利用者は、すべての顕微鏡で3時間:24,000円、AIVIAは1時間:8,000円)も課しております。
予約キャンセルでの利用料金に関して
以上の利用料金は、消耗品や電気代からの算出値で、すなわち「実際の機器の利用」に対して発生いたします。そのため、早い段階で利用の取消しの連絡が寄せられた場合は、原則として利用料金は徴収いたしません。
しかし以下のような場合は、他の利用者の利用機会の消失にあたるため、システムでの予約時間に相当する利用料金を課します。その顕微鏡の混雑度合いや、キャンセルした時間帯に実際に利用があったかの有無は、一切考慮しません。
- そもそも、連絡なく来ないとき.
- 利用開始時刻より、24時間前以降の直前の取消し.
- 数日間など長期間予約を行いながら、ごく一部のみの利用.
*いつサンプルが準備できても使えるよう、「とりあえず長めに、3日間おさえとくか!スケジュール決まれば、残りはキャンセルしよう!」といったところと推測されますが、他に顕微鏡を使いたい方にとっては、無為に振り回されただけで、著しい迷惑となります。この場合、「すべての予約時間」を課金対象とすることを、あらかじめ認識ください。 - システムから予約を行ったが、機器を全く利用しない、解析のみの利用.
*機器を使いたい方が優先です。解析でパソコンを利用したい場合は、スタッフにご相談ください。 - キャンセルが相次ぐ場合は、最初の取り消しから30日以内で3回め以降のキャンセル.
トライアル観察を行ってみよう
最初に初回利用者講習を行いますが、できる限り、実際に観察したいサンプルをお持ちください。実際のサンプルがありますと、この段階で、私たちスタッフとともに、少なからず観察条件等の最適化も行えると思います。ただし培養細胞サンプルの持ち込みに関しては、以下の[サンプル持ち込み方法と注意点]を、必ずご覧ください。
利用にあたっての注意事項は、[利用にあたっての注意点](約5MのPDFファイル,2024年6月更新)にもまとめております。
初回利用講習は、スタッフが丁寧に説明いたしますので、顕微鏡に初めて触れるような初心者の方でもご安心ください。もちろん講習以降も、操作方法に不明の点などがあれば、いつでも対応しますので、気軽にスタッフまで声をかけてください。
ただし人数が多くなりますと、ゆきとどいた説明が難しくなります。そのため、一度に3名まででお願いいたします。それ以上の大人数への操作説明をご希望の場合は、2回以上に分けて対応しますので、優先順位の高い方(=早々に使いたい方)3名を検討ください。
そして、当センターの機器で目的の観察ができるか確認したい場合も、まずはご相談ください。高速な現象のタイムラプス観察や超解像観察といった、かなり応用的な観察であっても、スタッフが機器を操作しますので、スムーズに検討できると思われます。
なお当センタースタッフからの初回講習を受けていない方は、一切の利用を認めません。
北大の機器利用システムへの登録方法。
北大では、早い段階から機器の共同利用化がすすめられました。そのため機器の共同利用システム(オープンファシリティ)が確立しており、機器の利用申請、初回利用の依頼、利用予約など、すべてオンラインで操作が可能です。
ただし利用にあたっては、北大の教職員番号(SSO-ID)をお持ちの教員(利用責任者)が、学生など(利用者)を登録する必要があります。学外利用者も概ね同様ですが、確認のため少し時間がかかる可能性があります。システムへの登録については無料ですので、早めに利用登録を行うことをおすすめいたします。
次に利用責任者が、利用者に「システムに登録されている機器の中から、利用してよい装置」を指定します。
申請内容を考慮してスタッフが承認を行うと、機器利用(予約)が可能になります。
また担当教員は、研究室秘書などを「補助担当者」とすることも可能です。補助担当者は、学生などの登録や利用料金の財源指定などを、教員に代わって行えますので便利です。
以下では、学内と学外の研究者に分けて、システムでの登録方法を記載します。
またシステムの使い方については、オープンファシリティでシステムの利用案内を作成しておりますので、こちらをご覧ください。「総合版 利用案内」からダウンロードも可能です。
また、学生の登録方法については、私たちでも簡単な「北大の学生の登録方法マニュアル」(約2MのPDFファイル、2025年6月更新)を作成しましたので、参考となりますならば幸いです。
学内研究者の登録方法
学内の方は、こちらをクリックして展開してください。
教員である利用責任者が、総合研究基盤連携センター(Global Research Facility Alliance Center: GFC)内のオープンファシリティのWebサイトにアクセスします。左上の[ログイン]をクリックし、[SSO-ID ログイン]より、SSO-IDを入力してシステムにログインしてください。
[北海道大学:オープンファシリティ]
[マイページ]で、”利用者一覧・追加登録”を選択しますと、利用者一覧の箇所に、”利用者の登録”がありますので、そちらで利用者の登録を行います。各種情報を記入して登録を押しますと、利用者にシステムから認証メールが届きます。そちらに沿って対応してもらうと、正式に登録されます(一度に1名しか登録できないうえ、部局の選択が少し大変なため、少しお手数をおかけすることとなりますが…)。
もし利用責任者自身も機器利用を希望される場合は、”自身を利用者として登録“をお願いいたします。
先にも触れましたように、秘書などを補助担当者とすることも可能です。利用者登録や、3:使用機器の選択など、一連の操作は補助担当者も行えますので、(教員の方には)便利と思われます。
こちらは、[マイページ]の”登録情報編集:補助担当者:補助担当者の新規登録”で、秘書にも同様に認証を行ってもらいます。
*利用責任者は、“誰の予算で機器を使うか?”を、まずは基準としてください。
例を挙げますと、助教が教授の予算で機器を使う場合は、上記の手順で教授に登録してもらってください。
一方、助教が自分の予算で使う場合は、「助教自らが利用責任者」となります。そのためSSOでログインし、上記の”自身を利用者として登録”で、お願いします。
次に、[マイページ:利用許可装置の選択]で、学生が利用してもよい装置を選択します。この操作は、[装置一覧(申請・講習・予約など)]では行えませんので、ご注意ください。
ただし、この[利用許可装置の選択]の初期設定では、すべての装置がリストアップされますので、装置を探すのが大変ですので、キーワードを入力して検索してもらうほうがよいかと思います。キーワードとしては、以下の装置番号を用いるか、あるいは「ニコン 顕微鏡」とするのがよいでしょうか。
機器リストが表示されますと、左端のチェックをつけて、「利用を許可する」を押してもらうと、許可状況:”許可あり”となり、その装置を学生が使うことを許可されます。
当センターの各装置の番号は、以下となります。
| AP-100104 | Station-1 高速レーザー共焦点顕微鏡 |
| AP-100105 | Station-2 TIRF/CSUのシステム |
| AP-100106 | Station-3 多色蛍光タイムラプス顕微鏡 |
| AP-100160 | Station-4 超高速共焦点顕微鏡 (新型機のほう) |
| AP-100258 | Station-5 超解像顕微鏡 (N-SIM) |
| AP-100293 | Station-6 高速多光子レーザー共焦点顕微鏡 (2光子顕微鏡) |
| AP-100311 | AI画像解析システム AIVIA |
※「その装置を、学生が使うことへの許可」になりますため、許可あり=学生に利用の許可を与えた機器、 許可なし=学生に使わせない機器、にあたります。
ただし実際に装置利用が可能となるのは、操作指導が無事に完了し、装置担当者が「この利用者ならOK。自身で予約して使ってよい」と、承認を出してからとなります。
※以下は、利用者、または”自身で利用する教員”が行う作業となります。
上記2で利用責任者にユーザー登録をしてもらうと、メールが届きますので、そちらに沿って認証を行ってください。
登録が完了しますと、”GFC-ID”というIDとパスワードが発行されます。ただ初期パスワードはランダムな文字列となりますので、変更したい場合/忘れた場合は、以下から再設定が可能です。
[総合研究基盤連携センター(GFC):パスワード再設定]
以下のシステムで、左上の[ログイン: GFC-ID ログイン]より、GFC-IDを入力してシステムにログインしてください。
[北海道大学:オープンファシリティ]
[マイページ:利用できる装置一覧]から、担当教員が利用を認めている機器を選び、”利用申請”を押してください。
もし表示されていない場合は、利用責任者に再確認してください。
装置担当者がシステムで承認しますと、以降は[装置一覧(利用申請・講習・予約)]を選ぶと”初回講習申し込み”または”予約”が表示されるようになります。 このときに、[予約可能な機器のみ表示]にチェックを入れて検索を実行しますと、楽になります。
なお学内研究者の利用料金のお支払いは、学内の事務担当者から、概ね四半期に一度程度、予算の振替の依頼がありますので、そちらのご対応をお願いいたします。
予算の締め切り等の関係で、3か月も待てない!という場合は、臨時の対応も可能ですので、スタッフまでご相談ください。
学外研究者の登録方法
学外の方は、こちらをクリックして展開してください。
利用責任者に該当する方が、総合研究基盤連携センター(Global Research Facility Alliance Center: GFC)内のオープンファシリティのWebサイトにアクセスします。左上の[New User]をクリックし、[3-2-2. 学外の方]より登録をお願いいたします。
利用内規の確認や登録者情報を入力した後、他の利用希望者の登録も行います。ここでは10名まで一度に登録できますが、もちろん後で追加・削除も可能です。
ただしシステムでの入力から登録完了まで、少し時間がかかる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
[北海道大学:オープンファシリティ]
登録が完了いたしましたら、次にログインして左上の[アカウントサービス]を押して選択、または左のリストから、[マイページ]を選択して、マイページに進んでください。
[マイページ:利用許可装置の選択]で、ご自身あるいはメンバーが利用してもよい装置を選択します。この操作は、[装置一覧(申請・講習・予約など)]では行えませんので、ご注意ください。
ただし、この[利用許可装置の選択]の初期設定では、すべての装置がリストアップされますので、装置を探すのが大変ですので、キーワードを入力して検索してもらうほうがよいかと思います。キーワードとしては、以下の装置番号を用いるか、あるいは「ニコン 顕微鏡」とするのがよいでしょうか。
機器リストが表示されますと、左端のチェックをつけて、「利用を許可する」を押してもらうと、許可状況:”許可あり”となり、責任者の方がその装置の利用を許可したこととなります。
当センターの各装置の番号は、以下となります。
| AP-100104 | Station-1 高速レーザー共焦点顕微鏡 |
| AP-100105 | Station-2 TIRF/CSUのシステム |
| AP-100106 | Station-3 多色蛍光タイムラプス顕微鏡 |
| AP-100160 | Station-4 超高速共焦点顕微鏡 (新型機のほう) |
| AP-100258 | Station-5 超解像顕微鏡 (N-SIM) |
| AP-100293 | Station-6 高速多光子レーザー共焦点顕微鏡 (2光子顕微鏡) |
| AP-100311 | AI画像解析システム AIVIA |
※「その装置を、利用者が使うことへの許可」になりますため、許可あり=利用の許可を与えた機器、 許可なし=使わせない機器、にあたります。
ただし実際に装置利用が可能となるのは、操作指導が無事に完了し、装置担当者が「この利用者ならOK。自身で予約して使ってよい」と、承認を出してからとなります。
※以下は、利用者、または”自身で利用する教員”が行う作業となります。
上記2で利用責任者にユーザー登録をしてもらうと、メールが届きますので、そちらに沿って認証を行ってください。
登録が完了しますと、”GFC-ID”というIDとパスワードが発行されます。ただ初期パスワードはランダムな文字列となりますので、変更したい場合/忘れた場合は、以下から再設定が可能です。
[総合研究基盤連携センター(GFC): パスワード再設定]
以下のシステムで、左上の[ログイン: GFC-ID ログイン]より、GFC-IDを入力してシステムにログインしてください。
[北海道大学:オープンファシリティ]
[マイページ:利用できる装置一覧]から、利用責任者が利用を認めた機器を選び、”利用申請”を押してください。
もし表示されていない場合は、利用責任者に再確認してください。
装置担当者がシステムで承認しますと、以降は[装置一覧(利用申請・講習・予約)]を選ぶと”初回講習申し込み”または”予約”が表示されるようになります。 このときに、[予約可能な機器のみ表示]にチェックを入れて検索を実行しますと、楽になります。
なお学外研究者の利用料金のお支払いについては、学内の事務担当者から、概ね四半期に一度程度、請求書が送付されますので、そちらよりご対応をお願いいたします。もちろん、いきなり請求書が届くわけではなく、準備段階で確認の連絡が行われる見込みです。内容確認等の必要がございますなら、その際にご連絡ください。
決算等の関係から、早々の請求等の対応を希望される場合は、私たちまでご連絡ください。概ね対応可能ではありますが、請求書の発行や発送作業の関係上、十分に早い段階での連絡をおすすめいたします。
利用前の確認事項
利用者登録が完了して、”正式なユーザー”となるまでは、原則としてオリジナルデーターの持ち出しや、直ちにそのまま利用可能な形式での持ち帰りは認めておりませんので、ご了承ください。「イメージングセンターでのトライアル観察で取得」といった文字を挿入した画像/動画ファイル等に限り、許可します。
トライアル段階のはずだった観察画像が無許可で発表された…など、当センターが望ましくない事例が過去にありましたため、ご理解ください。
また当センターの顕微鏡システムは、さまざまな観察目的に応じて使い分けることが可能です。一例として、まずStation-3(蛍光顕微鏡)の利用を希望したものの、Station-4(共焦点)のほうが適していることがわかった―という事例も多いです。あるいは、当センターの機器で良好な顕微鏡画像が取得できることが確認されたため、研究室の他のメンバーも利用を希望する、新規配属となった学生も利用させたい、といった相談も頻繁にいただきます。
操作説明のたびに初回利用講習料(24,000円)をいただくのも恐縮ですので、「当センターを継続して利用している研究室」は、2回め以降の初回利用講習料は不要です。1名のみにでも、あるいは何回でも初回指導も行いますので、「都度めんどうをかけて申し訳ない…」などと遠慮しなくても全く大丈夫です。操作説明を行った研究者の数、操作説明会の数が多いほど、私たちの実績にもなりますので、むしろ多くなるほうが大歓迎です。
なお”継続利用”のめやすは、直近の利用が1年以内とお考えください。さすがに利用が1年以上空きますと、新規ユーザー扱いとなる…と考えてください。
装置の初回利用講習と当センターの利用については、以下のルールを厳守ください。
特に2項めにご注意ください。つまり、ユーザーが操作指導を他の人に行うと、その研究室全体の利用ができなくなる可能性があります。
同じ研究室の学生のデーターを至急で撮りたい!というような事態となれば、ぜひスタッフに依頼してください。全力を尽くして、ベストな画像を撮ります!
- 当センタースタッフが初回操作指導を直接実施し、許可を得たユーザーのみが機器利用が可能であり、それ以外の者には利用を一切、認めない。学部・大学院教育において指導的立場のある教職員等の指示があったとしても、一切、認めないものとする。
- スタッフでないにも関わらず、他の者に初回操作指導を行ったと称して他者に利用させた場合には、該当課題の利用許可を取り消す。学部・大学院教育において指導的立場のある教職員等の指示によるものであっても、例外は無い。
- 使用許諾の無い時間帯に、スタッフの許可の無く入室することは、目的を問わず厳禁とする。
当センターへのサンプルの持ち込み(特に培養細胞)に関しては、別ページにまとめましたので、こちらをご覧ください。
機器の予約利用
利用登録が完了いたしましたら、GFC-IDとパスワードでログインし、[マイページ]の装置一覧から、随時予約を行って構いません。
[北海道大学:オープンファシリティ]
そして[機器詳細: 予約する]から、利用を希望する時間を登録してください。このときに当センタースタッフのスケジュール(不在・対応不可など)も確認できますので、操作説明を受けた直後など、まだ機器利用に自信がない方は、参考としてください。
誰が実際に装置を利用する予定かを明確とするため、[実際に利用する方のIDで予約を行う]ことをお願いします。
このため、一人のID(担当教員のIDなど)を皆で使いまわすことは、できればご遠慮ください。
予約については、8時間以内の利用は、最大で3回まで、8時間以上の利用は1回のみでお願いいたします。ただし顕微鏡の混雑度合いによっては、それ以上の予約も可能です。そうした状況なども含めて、いつでもスタッフまでご相談ください。
予約を行いましたら、そちらのスケジュールに合わせて、当センターまでお越しください。
スタッフはほぼ常駐しておりますので、わからない点があれば、あるいは操作説明を受けた内容以外で試したい観察などがあれば、いつでもご相談ください。